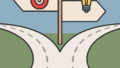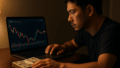消防設備士乙4を勉強したことで電気に興味が湧き、次は第二種電気工事士を受けてみたいと思うようになりました。
正直お金はないけれど、資格を取れば今後役に立ちそうだし、勉強の習慣も続けたい。
そこで今回は試験の概要と費用について調べてみました。
1. 第二種電気工事士とは?
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗などの電気工事を行える国家資格です。
電気工事の基礎を学ぶ入門資格であり、就職・副業・DIYに役立つとして人気があります。
2. 試験概要(2025年度の例)
- 受験手数料:9,300円
- 試験形式:学科試験+技能試験
- 学科試験:マークシート形式、一般用電気工作物に関する基礎知識を出題
- 技能試験:与えられた配線課題を制限時間内に正しく施工できるかを実技で判定
2025年度のスケジュール例:
・受験申込:3月17日(月)〜4月7日(月)
・学科試験:CBT方式 4月21日(月)〜5月8日(木)/筆記方式 5月25日(日)
・技能試験:7月下旬(予定)
👉 受験申込は試験の約2か月前に締切となるので要注意です。
合格率の目安
第二種電気工事士試験の合格率は、例年おおむね学科試験で60%前後、技能試験で70〜80%前後です。
全体で見ても合格率はおよそ50〜60%あり、国家資格の中では比較的合格しやすい部類に入ります。
ただし技能試験は工具不足や作業の手順ミスで落ちるケースもあるため、練習は必須です。
3. 受験にかかる費用
受験料よりも工具代や練習セットの費用が大きいのが特徴です。
- 受験手数料:9,300円
- テキスト・過去問:2,000〜4,000円
- 工具一式:約10,000円〜(専用セットを買うとさらに高い)
- 技能試験用練習部材セット:約24,000円(1回分12,000円 ×2回分が目安)
つまり、トータルで受験料より工具や部材代の方が高いのが現実です。
特に練習セットは高額なので、私は必要な部材だけ個別購入して節約しようと思っています。
4. 勉強期間の目安
学科+技能の両方を見据えると、勉強期間は約2か月が目安です。
2026年5月の受験を目指すので、私は2026年3月から勉強開始にする予定です。
5. まとめ
第二種電気工事士試験は、受験料は安いが工具・部材代が高いという点が最大のハードルでした。
とはいえ、資格を取れば将来の選択肢が広がるので、2026年の上期に挑戦しようと思います。
来年の5月に試験を受ける予定なので 3月ぐらいから勉強しようと思います。合格率は消防設備士より高いので結構余裕だと思いますが、実際に勉強してみないとまだ分かりません。
学習期間は2か月集中で、費用は可能な限り節約しつつ取り組んでいきます。
まあ今年はもう勉強はしないので、来年からしっかり頑張りたいと思います。