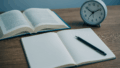1. 導入
40歳を迎えた自分は、かつてネットワークエンジニアとして監視業務をしていました。システム障害がないかを常に見張る夜間シフトが中心で、昼夜逆転の生活が続いた結果、体調を崩してしまいました。そこから正社員として働く道は難しくなり、生活を支えるためにウーバー配達員の仕事に切り替えました。
ウーバー配達員としての生活は3年ほど続けています。人間関係のしがらみがなく、好きな時間に働ける気楽さはありましたが、収入をウーバー一本に頼ると不安定です。特に春や秋は需要が落ち、報酬が少なくなって低収入になることも珍しくありません。自由ではあるけれど、将来性はゼロに近いと感じ、不安がどんどん大きくなっていきました。
そんなとき、ある記事で芸人が消防設備士の資格を取ってバイトしている話を目にしました。調べてみると「消防設備士」という仕事があり、資格を持っていればアルバイトでも日給が高く稼げることを知りました。「40代で今さら勉強を始めても遅いのでは」と迷いもありましたが、人生80年と考えればまだ半分残っている。やらない後悔より挑戦だと思い、受験を決意しました。
2. 受験を決めた理由
消防設備士乙4を選んだのは、バイトでも日給が高く、経験を積めば正社員への道もあるとわかったからです。さらに受験資格に年齢制限がないため、40代からでも挑戦できるのは大きな後押しになりました。
勉強時間の確保についても、ウーバー配達員という働き方は相性が良いと感じました。午前中の配達前に1〜2時間を勉強時間として固定できるのです。生活リズムを崩さずに継続できるとわかり、「これなら自分でも続けられる」と確信しました。
また、使用する教材は『消防設備士第4類(甲種・乙種)〈令和5年 上下巻〉』の2冊に絞ると決めました。無駄にテキストを増やさず、繰り返しやり込む方が効率的だと判断したからです。
3. 勉強開始(1〜3週目)
6月末に『消防設備士第4類(甲種・乙種)〈令和5年 上下巻〉』をネットで注文しました。届いたテキストを開いて最初に感じたのは、電気の基礎だけで100ページ近くもあるのか…という圧迫感でした。ただ、消防関係法令や設備等の構造については「これは暗記でなんとかなる」と思えたので、まずは苦手意識の強い電気以外から手をつけることにしました。
勉強場所は家ではなく図書館にしました。理由は単純で、電気代を節約して夜しかクーラーを使わない生活をしていたため、昼間の部屋は暑くて勉強どころではなかったからです。夏休み中で学生が多い時期でしたが、朝イチで行けば比較的空いていたので、午前中に席を確保して2時間ほど集中するようにしました。午後は配達の仕事があるため、勉強は割り切って午前だけ。生活のリズムに組み込みやすく、勉強の習慣もつきやすかったと思います。
勉強のやり方はシンプルで、法令と構造に関してはテキストを読んで覚えるのを基本にしました。一方で、電気の計算問題や実技試験の名称問題は「書いて覚える」ことを徹底。読んだだけでは頭に残らないし、本番で正しく書けないと点にならないからです。この2つのスタイルを使い分けながら、午前中の図書館での勉強を進めていきました。
4. 中盤(4〜6週目)
毎日勉強する習慣がついてきたので、思ったよりも順調に進みました。ただ、やはり電気の範囲は広すぎると感じました。全部を理解しようとすると時間が足りないし、頭にも入りません。そこで、この段階で「頻出問題以外は捨てる」と割り切ることにしました。
一方で、消防関係法令と構造・機能および工事・整備については、過去問を解いてみると大体似たような内容が出題されていることがわかりました。暗記さえしてしまえば点が取りやすい分野だと実感でき、ここで確実に得点を稼ごうという方針に切り替えました。実技対策については、「なんとなく覚えている」状態だといざ記述しようとしたときに全く手が動かないことが多かったです。そこで「書いて覚える」ことを徹底するようにしました。
この時点での戦略は、電気は最低限40%クリアを目標にし、法令と構造等で点数を稼ぐ。苦手を無理に克服するよりも、得点源を確実に固めて合格点に届かせる作戦を取るようになりました。
5. 直前期(7〜8週目)
試験一週間前からは本気で追い込みに入りました。ここで落ちたら今までの勉強時間がすべて無駄になるし、次の受験までの期間を考えると機会損失が大きすぎると感じたからです。そこで、この一週間だけは午前と午後に分けて合計5時間ほど勉強することにしました。
勉強方法はシンプルで、過去問を一通り解き直し、できなかった問題には付箋を貼って徹底的に潰していきました。特に法令と構造・機能は付箋がどんどん減っていき、自分の成長を実感できたのは励みになりました。一方で電気に関しては最後まで割り切り、頻出問題だけを繰り返すことにしました。「満点を狙う必要はない、最低限40%を超えればいい」という意識で、効率重視の戦略を徹底しました。
6. まとめ(前編)
こうして勉強を始めてから試験直前までの8週間を振り返ると、正直すべてが計画どおりに進んだわけではありません。疲れてサボった日もありましたし、電気の分野では理解できない部分を思い切って捨てたこともありました。それでも毎日少しずつ勉強を続ける習慣をつけられたことが、一番の収穫だったと思います。
特に「法令」と「構造・機能」を中心に固め、電気は最低限の40%を狙うという戦略の切り替えが、自分にとって現実的で合格へつながる道でした。そして実技に関しては「覚えたつもりでは書けない」ということを痛感し、書く練習を取り入れたのも大きな一歩でした。
次はいよいよ試験当日と合格発表の記録です。本番の様子、持ち物、時間配分、そして結果が出るまでの不安な日々については「後編」で詳しくまとめています。