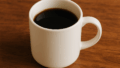1. 導入
前編では勉強開始から試験直前までの流れをまとめました。ここからは試験当日と合格発表までの体験です。振り返ってみると、直前期にはやるだけのことはやったという気持ちが強く、緊張感よりも「ギリギリ合格できそうだ」という開き直りに近い心境でした。
2. 試験当日の背景と準備
受験会場は中央試験センター。自宅から電車でおよそ1時間ほどかかりました。土曜日だったので電車は混んでおり、久しぶりの人混みに試験前から少し疲れてしまいました。駅から会場まで歩くだけでも真夏の暑さで体力を削られたのを覚えています。
持ち物は受験票・筆記用具・過去問とシンプル。会場を見渡すと年配の受験者が多く、女性は目立つくらい少なかったのが印象的でした。
3. 試験当日の体験
筆記試験は法令・電気・構造等に分かれていました。手ごたえは次のような感じです。
- 法令:過去問通りの問題が多く、落ち着いて解けた。得点源になった感触。
- 電気:5問中2問はできたと思うが、残りの3問は分からず。とりあえずマークシートを埋めて流した。
- 構造・機能:こちらも過去問通りで、特に困らず対応できた。
続く実技試験では、過去問と同じ問題が3問出て手応えはあったものの、残り2問は微妙な出来でした。記述なので不安は残りましたが、全体としては「最低限はできた」という感触でした。
時間配分には困らず、全体で1時間ほどで解き終わり退出しました。周りを見ても早期退出する受験者は多く、自分が帰った後も半分以上は会場に残っていました。
4. 合格発表までの心境
試験問題は回収されるため自己採点はできませんでしたが、感触的には「ギリギリ合格したはず」と確信していました。特に電気の2問と実技の3問は問題集で繰り返し見た内容そのままだったので、自分の手ごたえに根拠はありました。
5. 合格発表の日
合格発表は試験から約1か月後。正午すぎにネットで確認したところ、自分の受験番号が合格者一覧に掲載されていました。素直に嬉しかった瞬間です。翌日には葉書が届き、得点の内訳も判明しました。
- 法令:70%
- 基礎知識(電気):40%
- 構造・機能:66%
- 筆記全体:63%
- 実技:60%
やはりギリギリの合格ラインでした。電気と実技が合格基準すれすれだったのを見て、「もしあと1問落としていたら」と思うとゾッとしました。
6. まとめ(後編)
消防設備士乙4は、社会人・40代でも独学で十分に合格できる資格だと実感しました。ただし、電気と実技は油断すると落ちることも痛感しました。逆に言えば、法令と構造で確実に点を稼ぎ、電気と実技は「最低限クリアする」意識で臨めば突破可能です。
そして一番大事なのは、教材を増やさずに同じ問題集を繰り返すこと。迷わず基礎を固めることで、ギリギリでも合格ラインに到達できると身をもって学びました。